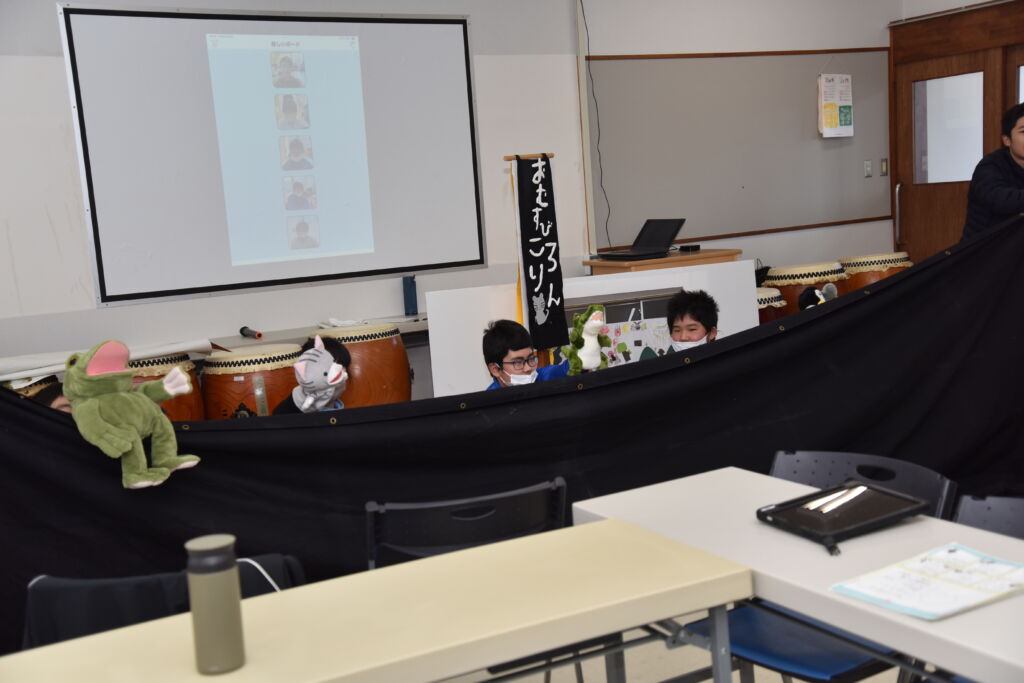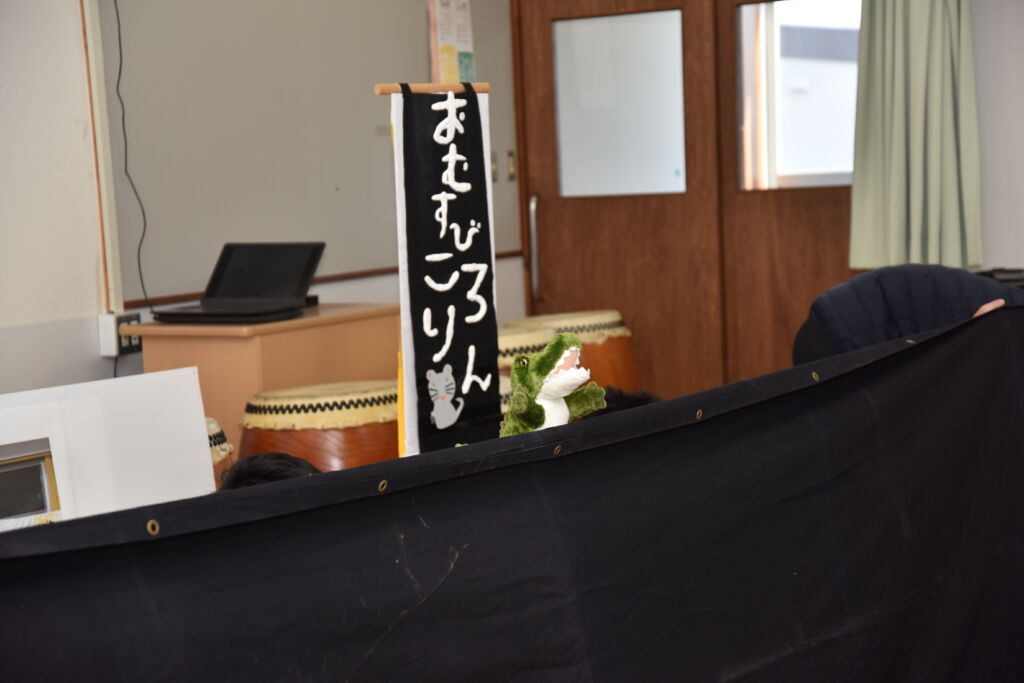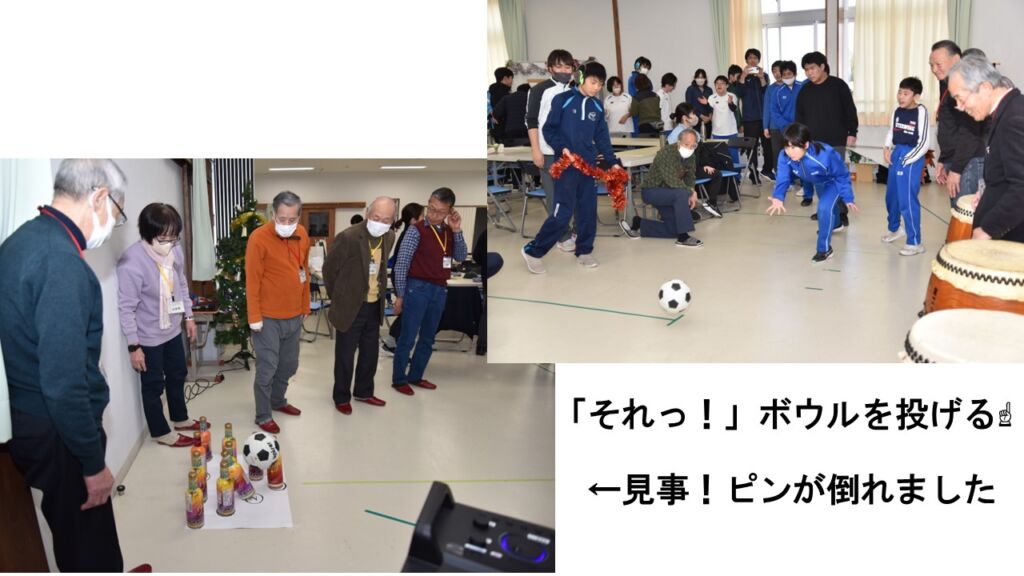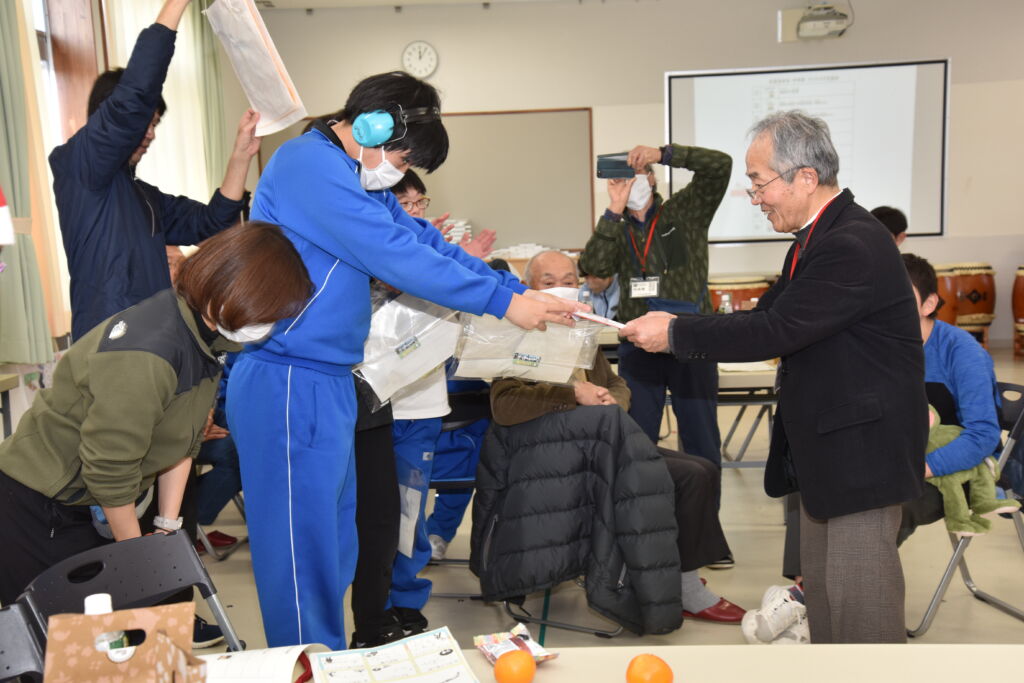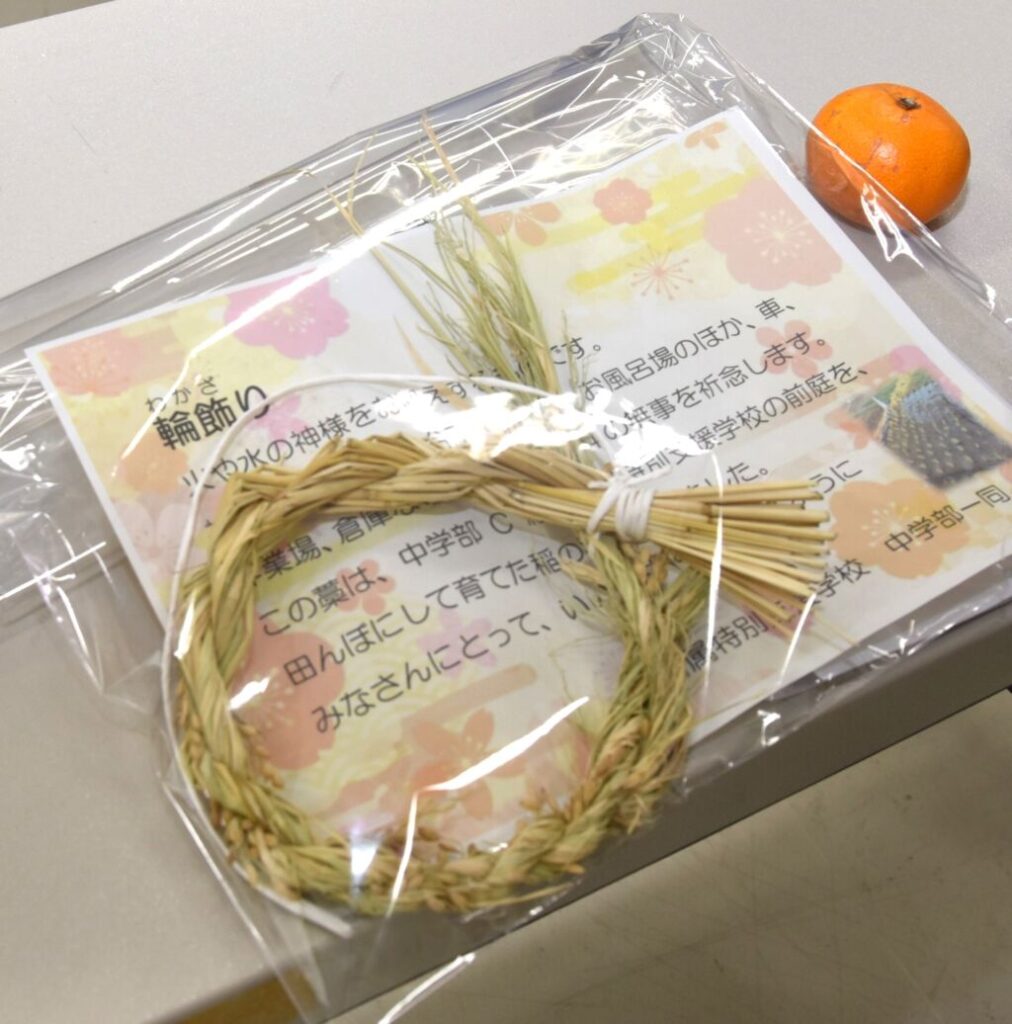石渡写真クラブ月例会(12月)作品&講評
明けましておめでとうございます。
穏やかな天候の初春、今年いっぱい続くといいなあと思いつつ・・・。
2日午後から雪がちらほら、いよいよ本格的な冬将軍到来か。
と思いきや、予報がはずれ、3日も本日4日も好天、穏やかなお正月が続いております。
今年も頑張ってまいりましょう。
講評は年を越しましたが、昨年最後12月の例会の作品&講評です。
昨年暮れ、第14回信毎フォトコンテストに宮澤一成さんが応募した作品が佳作に選ばれ12月27日の新聞に発表、氏名が掲載されました。おめでとうございました。
同コンテストは小生が在社時代に関わっていたことがある思い入れのあるコンテストです。入社した1971年直後に「(県内の)写真愛好家のレベル向上」を目的に信毎と県写真連盟共済で始まった歴史の長いコンテストです。数年前にはコンテストの名称、一年内の実施回数などを衣替えしましたが、ほぼ同じ内容で継承されて今に至っています。応募しやすさを考慮、毎回「テーマ」がありますが、今回のテーマは「交」でした。応募総数は248点。入賞、入選、佳作に選ばれるのは20数点ですので、狭き門といえば狭き門。その中に入った宮澤さんの作品は秀逸な一枚だったかと思います。
コンテストのために写真を撮るわけではありませんが、日ごろ写真を撮っている者にとっては「コンテスト」は一つの楽しみといいましょうか、撮った作品がどのように評価されるかを試すいい機会となる場です。ほかにも写真県展はじめ各自治体の観光フォトコンなどいろいろとあります。ぜひ、「これは!」という写真が撮れたら応募して“運”だめしをしてみましょう。
講評はクラブ員で講師の増田今雄さん(5常会)です。
写真をクリックすると拡大して見えます。
※作品の掲載順は「あいうえお」順、一回ごとに逆に紹介しています。
【宮澤一成】
 「秋の参拝」(上越市春日山林泉寺)=11月15日
「秋の参拝」(上越市春日山林泉寺)=11月15日
コメント:今年の朝陽史跡めぐりに参加したときの一場面です。ぞろぞろと皆で参拝をしてきました。
講評:お寺境内にまだ残る紅葉と参拝する人たちが程よくばらけ(散らばり)、バランスよくにぎやかな一枚にまとまりました。  「うまいカニ~」(糸魚川市マリンドーム能生)=11月15日
「うまいカニ~」(糸魚川市マリンドーム能生)=11月15日
コメント:史跡めぐりの昼食会の後、海を見に出てみるとカニを食らう人たちが大勢いました。
講評:ぼつぼつ寒い時期ですが、穏やかなブルーの海原を背景にテトラポットの上が舞台。うまそうですね。口をあんぐりとあけ、細長いカニをぱくり。いい瞬間を捉えました。
【牧内二郎】
 「冬囲い」(高田城址公園)=10月21日
「冬囲い」(高田城址公園)=10月21日
コメント:高田城址公園へ行きました。冬囲いの資材が置かれていたので、これは撮影のチャンスなのではと思い、公園内を散策してチャンスを待ちました。赤い服の作業員の方が笑顔で作業されてました。
講評:葉も落ちた冬枯れの桜の木と並行する中低木が雪で押しつぶされないように冬囲い作業。始まるタイミングを待って撮影した労作。アングルが真正面からなので、平板な感じですが、並木をやや斜めに狙うと、奥行き感が出たかと思います。
【広澤一由】
 「聳え立つクレーン」(運動公園)=11月28日
「聳え立つクレーン」(運動公園)=11月28日
コメント:墨盛んに組立てられていく新たな体育館の工事現場には、背の高いクレーンが活躍していた。竣工が待ち遠しい!
講評:真っ青な空のブルーに伸びるクレーンの赤白が対照的。その高さ、大きさが右のアクアウイングや左の総合体育館から推察できます。旧広場に建築という位置関係もよく分かります。手前にケヤキの落ち葉が見え季節感も盛り込めました。  「戦艦『三笠』にて遠い昔を偲ぶ」(横須賀)=11月14日
「戦艦『三笠』にて遠い昔を偲ぶ」(横須賀)=11月14日
コメント:日露戦争で活躍した旗艦「三笠」を見学し、ロシアのバルチック艦隊に勝利した遠い昔に思いを馳せた。
講評:港湾の一角に係留されているかつての戦争の戦艦。きれいに保存された感じと青い海を見ていると「平和が一番」と語り掛けているように思えます。
【中島弘】
 「えびす講花火」(長野市)=11月23日
「えびす講花火」(長野市)=11月23日
コメント:初めて花火の撮影を試みました。事前に調べた条件にカメラを設定し撮影しました。シャッターを押すタイミング、押している時間、暗闇から突然現れる光をファインダーに納める、等々体験から得られるコツを重ねていきたいと思います。
講評:私もかつてモノクロ時代に仕事で撮ったことがありますが、それ以外ではあまり狙わない素材です。が、よく目にする作品は、花火の下に何かを入れるものが多いです。遠くから狙って市街地の夜景、あるいは超接近して有料席のテントや人込みを入れ・・・。それぞれレンズ選択が違いますが、ぼつぼつと経験を積み重ねていってください。暗いですので足元、落とし物に注意してください。  「畑の紅葉」(長野市篠ノ井)=11月24日
「畑の紅葉」(長野市篠ノ井)=11月24日
コメント:目的の銀杏の紅葉を撮れず、移動中桃畑に遭遇。紅葉した落ち葉、不思議な枝の曲がりを撮ってみました。
講評:世の中、歩いているとそこそこに素材が転がっているものです。それに気が付くかどうか、絵になるぞとひらめくかどうか・・・だけです。その観察、洞察できる眼を養うことです。斜めに傾いた桃の幹と畑いっぱいの落葉が“小さな秋”を演出しています。
【竹内一郎】
 「猫が2匹」(自宅)=令和6年 コメント:我が家には猫が2匹います。ラグドールとシンガプールです。仲がいい時と悪い時がありまして、取っ組み合いもあれば、なでなでしているときもあります。私がさきに行くとまでは長生きしそうです。
「猫が2匹」(自宅)=令和6年 コメント:我が家には猫が2匹います。ラグドールとシンガプールです。仲がいい時と悪い時がありまして、取っ組み合いもあれば、なでなでしているときもあります。私がさきに行くとまでは長生きしそうです。
講評:種類の違う、太いのと細い猫が二匹。温かそうな部屋で高みの見物でしょうか、カメラ目線でポーズをとっています。洗濯ばさみなども傍にあって日々の生活感あふれる一枚となりました。
【高山三良】
 「アスリートは見ていた」(長野運動公園)=12月9日
「アスリートは見ていた」(長野運動公園)=12月9日
コメント:令和10年開催の国民スポーツ大会に向けて新体育館の建設が進んでいます。大活躍のクレーンと工事を見守る円盤投げ選手がありました。
講評:大空に高々と伸びるクレーン、着々と鉄骨が組みたてられて姿を現した新体育館。かつて昭和50年ごろに建てられた運動公園施設の一角にある記念のモニュメント「円盤投げ」を引っ掛け、新旧の時の移ろいを盛り込んだところがいいですね。  「ジョビちゃんのお遊び」(石渡=自宅)=11月3日
「ジョビちゃんのお遊び」(石渡=自宅)=11月3日
コメント:ジョウビタキが車の屋根から滑り落ちたと思いました。何度も何度も。リアウィンドーのスロープを利用してスライダーごっこをしていたんです。楽しそうに。
講評:何か小鳥が遊んでいるような感じが羽や体の動きから感じられます。面白い素材を発見、いろいろな角度から大小織り交ぜて組み写真にまとめました。が、起承転結が少し分かりにくいかなー?もう少し、時系列というか「こうなって、ああなった」的に分かりやすく組んだらもっと面白くなると思います。また来たら再挑戦を。
【後藤祥子】
 「信号の番長」(石堂町)=11月16日
「信号の番長」(石堂町)=11月16日
コメント:なぜか嫌われ者のカラス。ごみをあさったりと人間に害を与えている印象がある。「自分を見て」と言わんばかりに信号の上にいて「いいことをしているよ」と必死になっている姿を撮りました。本当は賢いカラスです。
講評:中央の信号機の上にいますが、向こうの街路樹の葉の色と同化してしまい分かりにくいです。光線状態はどんなあんばいだったです?カラスは羽が黒いのでカッと太陽光線が当たる時間帯、もしくは背景を後ろのビルの白にすると浮いて見えるかと思います。  「葉の個性」(自宅庭)=12月2日
「葉の個性」(自宅庭)=12月2日
コメント:秋も終わり冬になりました。木々の葉の個性を発揮し表現できるのは、秋なのですね。太陽に照らされ美しい見えたままを写したいのにまだ技術がおいつきません。今年の秋の一枚です。来年は少し上達したいなあ・・・
講評:真っ赤になった葉の色、きれいですね。後ろにはやや黄色のもあり・・・。色味をもっと鮮やかというか、太陽光線の反射をもう少し除くと違う発色となります。そうするには、PLフィルターというフィルターをかけてみましょう。別名「反射除去フィルター」といいま、テカテカした反射や水面に映った空の反射などを除いてくれて鮮明になります(なるはずです)。それと、ご自宅とはいえ、画面の中に少しだけでも主題の向こうに見える景色、街並みとかなんかを入れると“作品”により近付きます。
【小島真由美】
 「海で見る夕日」(神奈川県城ケ島)=11月23日
「海で見る夕日」(神奈川県城ケ島)=11月23日
コメント:長野県民の私にとって海に沈む夕日は滅多にみることができません。本当は水平線に沈む夕日を撮りたかったのですが、帰りの時間もあったのでオレンジ色に染まった海の夕日をとりました。城ヶ島はウィディングフォトが有名な場所で、この日4組の方が写真を撮っていました。その様子も映っています。
講評:向こうの岩の左側に写真を撮る人とカップルがいますが、岩の黒と重なってしまい分かりにくく残念です。岩の上にいてシルエットでもその様子が見えると点景として申し分ない作品になったかと思います。 
 「幻日」(神奈川県城ケ島)=11月23日 コメント:今年2回目の「お福分け」になります。幻日を見ると「幸運が訪れる前触れ」と言われています。皆さんにいいことが起こりますように。この写真(写真下)は色を調整したものになります。実際はIMG_9294(写真上)になります。どこまで加工していいのかわからずご意見ききたいです。 講評:いい場面に遭遇しました。ややマゼンタ(赤)色を調整し加工、夕焼けのイメージが増しいいかと思います。近年、あまりに極端に色調やコントラストなどを強調、本来の自然な感じが損なわれるケースが目立つ傾向にあります。気を付けましょう。後、トリミングですが、下の岩の面積が多すぎなのと逆に上の雲のある空間の上部をカットしましたが、下の岩の面積はもう少し少なめに、上の部分は元にしましょう。すると主題の幻日がもっと存在感を増してきます。
「幻日」(神奈川県城ケ島)=11月23日 コメント:今年2回目の「お福分け」になります。幻日を見ると「幸運が訪れる前触れ」と言われています。皆さんにいいことが起こりますように。この写真(写真下)は色を調整したものになります。実際はIMG_9294(写真上)になります。どこまで加工していいのかわからずご意見ききたいです。 講評:いい場面に遭遇しました。ややマゼンタ(赤)色を調整し加工、夕焼けのイメージが増しいいかと思います。近年、あまりに極端に色調やコントラストなどを強調、本来の自然な感じが損なわれるケースが目立つ傾向にあります。気を付けましょう。後、トリミングですが、下の岩の面積が多すぎなのと逆に上の雲のある空間の上部をカットしましたが、下の岩の面積はもう少し少なめに、上の部分は元にしましょう。すると主題の幻日がもっと存在感を増してきます。
【小池公雄】
 「満月捕食」(運動公園)=12月5日
「満月捕食」(運動公園)=12月5日
コメント:高山さんの投稿を見て、月が貯水塔に被る所を狙いに行きました。いざ構えてみると月の移動が意外に早くてまごついているうちに構図が予定と変わってしまいあわてました。月も貯水塔の先端ももっと輪郭がはっきり撮れる方法を教えて下さい。
講評:目の前の被写体はすぐそこで、月ははるか36万㌔の彼方。いくら被写界深度(絞り)を深くしても両方にピント合致は無理です。どっちかにフォーカスを合わせる、自分の主張したい方に合わせることでいいかと思います。その点で、この作品はご苦労なさったようですが、これでいいかと思います。はるか遠く霞んだお月さんを塔が「ぱくり」というイメージは出たかと思います。両方にピントを合わせる方法は「合成」という手法を使います。つまり塔にピントのあった一枚のカットと月にピントを合わせ、なお大きさも適度に大きくしたお月さんのカット、この二枚を一枚の写真の中に合わせてしまうというやり方です。方法はいろいろありますが、長くなるのでここでは割愛します。  「逃げろ逃げろ」(川中島古戦場)=12月7日
「逃げろ逃げろ」(川中島古戦場)=12月7日
コメント:秋の日暮れ近くに川中島古戦場に行ってみました。木々の葉は落ち、池の草も立ち枯れて、岸辺の木々とともに池に写り込んでいる中に鴨が対岸へ逃げる水紋をつくり、おもしろい線だなと思いました
講評:水面に写り込んだ冬枯れの木々の影がゆらゆらと、鴨の動きとともにきれいというか、初冬の風情を醸し出しています。カモの水紋もいいですが、むしろ木々の映りこみを中心に画角をトリミングすると別の感じの作品になります。  「寝鴨に冬間近」(川中島古戦場)=12月7日
「寝鴨に冬間近」(川中島古戦場)=12月7日
コメント:午後の弱い日差しの中で鴨が羽に頭をうずめて休んでいました。来る寒さに体力温存か?最初はどういう格好をしているのか分からず、不思議に見えました。
講評:お腹が満ちると?じっと動かず、コメント通り「体力温存」かと思います。羽毛をまとい暖かのはずですが、頭部を隠すように背中の方を向きます。みんな同じ格好をしているのでユーモラスです。望遠レンズによるものでしょうか、ややフォーカスが甘いです。手振れ防止にはご面倒でも三脚使用を。
【倉澤利和】
 「日向ぼっこ」(飯綱町)=10月28日
「日向ぼっこ」(飯綱町)=10月28日
コメント:リンゴ農園にバイトに行きりんごの葉摘みをしている時、りんごの上に乗っているカエルが目に入りました、こちらを見るのを待ってスマホで撮りました。
講評:仕事の合間によく見つけましたね。そして、それを作品にしようとカメラ目線になるまで待って収めた心意気がいいです。今はスマホという撮影の武器がいつも身近にあり便利な世の中、というか写真というものが生活の中に完璧に居座った時代ともいえます。とにかく、いろいろと難しい操作とか、いい写真とか何とかはそっちに置いて目の前にあるものを、身近なところにあるスマホで撮る、残す。これでいいのだと思います。と、カエルが問いかけているように見えます。
-726x1024.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-723x1024.jpg)
.jpg)





















-1.jpg)
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)